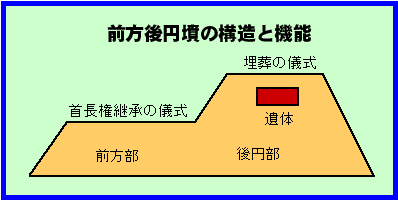新村出編『広辞苑』(岩波書店1976年第2版)を見ると、地名としての「から」には、次の二つが掲載されています。これが正解です。
いずれの言葉も、現代の若者用語としては死語となってしまいました。
それでも、このうち、①の方は、比較的有名でしょうか。唐(から)・天竺(てんじく)といえば、長く、直接には中国とインドをさす言葉として、使用されてきました。
②の方の、「広く外国の称」に関しては、少しでも多くの人に「ああ、あれか」といってもらえそうな例としては、「からゆきさん」があげられます。
これは、江戸時代末から昭和の初めにかけて、日本のあちらこちらから(とくに多いところは長崎県島原地方・熊本県天草地方)外国の娼館へ娼婦として出稼ぎに行った女性たちを示す言葉です。教科書には出てきませんが、映画などにはしばしば取り上げられた物語です。
映画では、次の作品の名が知られています。
『からゆきさん』 今村昌平監督 善道キクヨ主演 1973年
大場昇著『おキクの生涯』(明石書店2001年)の善道キクヨが、身の上を語ったものをフィルムに収めたものです。
『サンダカン八番娼館 望郷』 熊井啓監督 田中絹代 栗原小巻主演 1974年
山崎朋子の同名小説の映画化です。
『女衒(ぜげん)』今村昌平監督 緒方拳主演 1987年
河合譲著『村岡伊平治自伝』(1960年南方社)などをもとに、3000人の娘を売ったという、村岡伊平治をモデルにした映画です。
 詳しく調べるには、この道の研究の先達、大場昇氏のHP「からゆきさんの小部屋」が最適です。 詳しく調べるには、この道の研究の先達、大場昇氏のHP「からゆきさんの小部屋」が最適です。
これらの語源となった、「から」はどこの地域なのでしょう。
正解、からはもともと、古代朝鮮半島南端の地名なのです。
つまり、4世紀から6世紀にかけて、朝鮮半島の南端部分の地域にあった小国群が、加羅(から)です。これは、「加耶」または、「伽耶」と書かれる「かや」と同じです。『日本書紀』ではこの地域のことを、「任那」と読んでいます。
この言葉が、やがては、「韓」と書いてからと読み、朝鮮の総称となり、さらには、唐と書いて中国の意味となり、そして、近代においては、外国と同じ意味にまで拡大されていきました。
加羅というと、上述の、『日本書紀』の「任那」の記述の問題があります。
これについては、新しい学説の主流は、次のようになっています。
「『書紀』(日本書紀のこと)は、加耶諸国を好んで「任那」とよんだ。また、教科書でも、最近でこそ「加羅」とか「加耶」とか記されるようになったが、以前はもっぱらこの語が用いられたので、現在でも、筆者より少し下の世代ぐらいまでの読者は、「任那」の方がなじみ深いのではないかと思う。しかし民衆のなかではぐくまれていったカラに対し、「任那」はおよそ対局にある語であり、倭王権の独尊的立場の生み出した、政治臭のプンプンする言葉なのである。
ほんの20~30年ほど前まで、日本の古代史学界では、日本はヤマト朝廷が成立して間もない四世紀後半には朝鮮半島南部に武力進出し、そこに政治機関として「任那日本府」をおき、朝廷の「官家」(みやけ)として「任那」を植民地のように支配・経営した、その支配は562年の「任那の滅亡」までつづく、とする考えが不動の定説であった。このような見解は、現今の学界では、さすがに影をひそめつつあるが、一般には、まだまだ影響力をもっているのではなかろうか。(中略)
『書紀』は「任那」という語を、しばしば加耶諸国の汎称として用い、しかもこの「任那」の地は、朝廷の「官家」であると主張する。そこで、「官家」を朝廷の直轄領の意味に解し、『書紀』の記述を素直に受け取ると、加耶の全域があたかも朝廷の支配下におかれていたかのように理解されることになる。しかし、実際には倭国は加耶諸国に対して一定の政治的、軍事的影響力はもっていたものの、支配していたわけでは決してないし、加耶諸国は小さいながらも政治的独立を保っていた。『書紀』の任那に関する記述は、その編纂主体である日本の古代国家の政治的立場の忠実な表明ではあっても、決して客観的事実ではないのである。それを事実と信じると、みすみす『書紀』編者の術中におちいってしまうであろう。」
※熊谷公男著『日本の歴史03 大王から天皇へ』(講談社2001年)P23~24
|
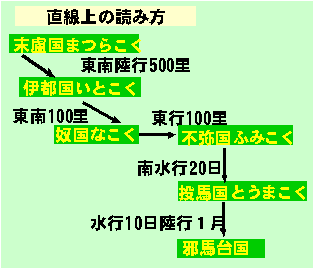
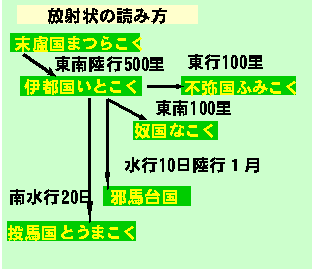
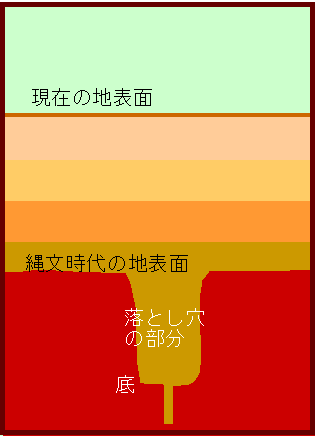





 建設後しばらく時間がたつと、墳丘上の石は脱落し、表面には草が生え、さらに時がたてば、木が生い茂ります。
建設後しばらく時間がたつと、墳丘上の石は脱落し、表面には草が生え、さらに時がたてば、木が生い茂ります。 
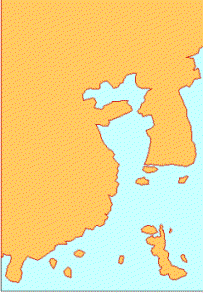 にして描かれています。ついでですが、北海道は描かれていません。つまり、中国人は、魏志倭人伝の時代も、元・明の時代も、日本列島を南北に長い島としてとらえていたと考えられます。
にして描かれています。ついでですが、北海道は描かれていません。つまり、中国人は、魏志倭人伝の時代も、元・明の時代も、日本列島を南北に長い島としてとらえていたと考えられます。