目から鱗 銃砲と歴史3 高島秋帆と高島平
| | メニューへ | | | 前へ | | | 次へ | | | P1参考文献へ | | | P1地図へ | | | P8写真集へ | |
| 銃砲と歴史3-6 |
| 銃砲と歴史について、シリーズで取り上げます。 |
| 高島秋帆と高島平6 西洋火砲の発展と日本110/02/14 作成 |
| 高島秋帆の演習時、その火砲は西洋砲術史のどの位置に | このページの先頭へ | |
|
高島秋帆が徳丸ヶ原で演習を行ったのは、1841年のことです。 |
| 具体的な問題提起 | このページの先頭へ | |
|
銃の専門家やマニアの方はよくご存じでしょうが、私も含めて、普通の方は、何が問題なのかよく分からないこともおありかと思います。 |
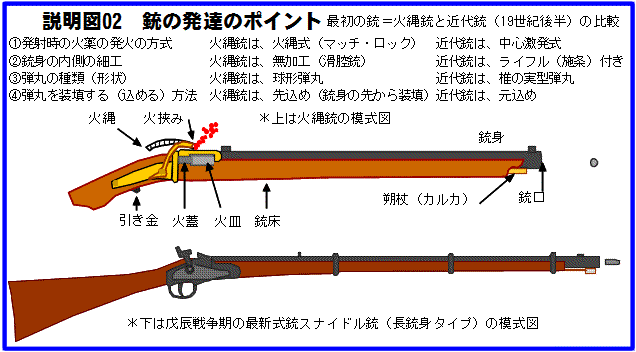
| 銃の発達のポイントの説明1 | このページの先頭へ | |
|
以上の4点が、15世後半に誕生した火縄銃から、近代的な銃が生まれた19世紀後半へかけての400年ほどの間の銃の発達のポイントです。 |
|
※このページは、以下の書物等を参考に記述しています。 |
| ①発射時の火薬への発火方式 | ||
|
銃砲の場合、弾丸は火薬の爆発で発射されます。その火薬をどのような方法で発火・爆発させるかが第一のポイントです。
|
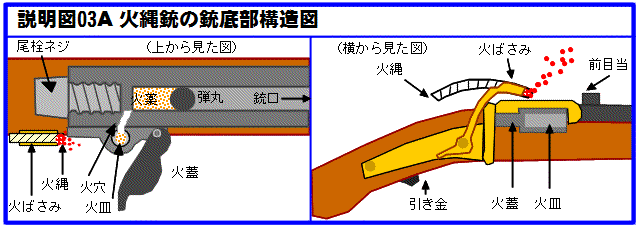
|

|
※火打ち石については、目から鱗:江戸時代の生活「火打ち石にについて確認する」で説明しています。→ |
|
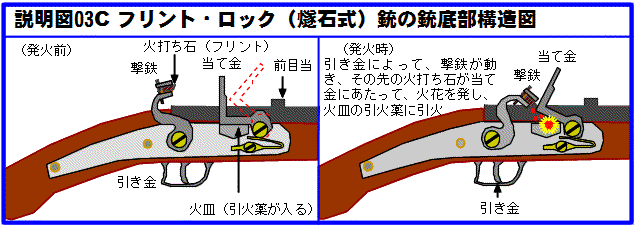
|
ここで日本史との関係で、一つ重要なことを示します。このことは、日本史ではあまり意識されていないことです。 |
|
|

|
ポイントの①~④のうち、やっと一つ説明しました。一つ一つ絵や写真の説明で、時間がかかることかかること。(+_+) |
| | メニューへ | | | 前へ | | | 次へ | | | P1参考文献へ | | | P1地図へ | | | P8写真集へ | |