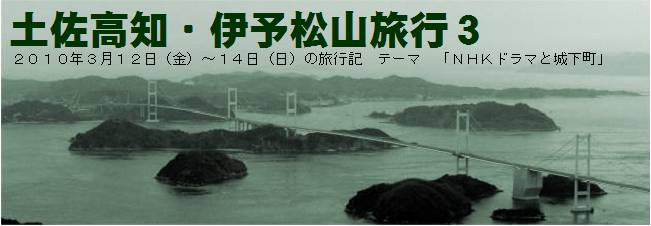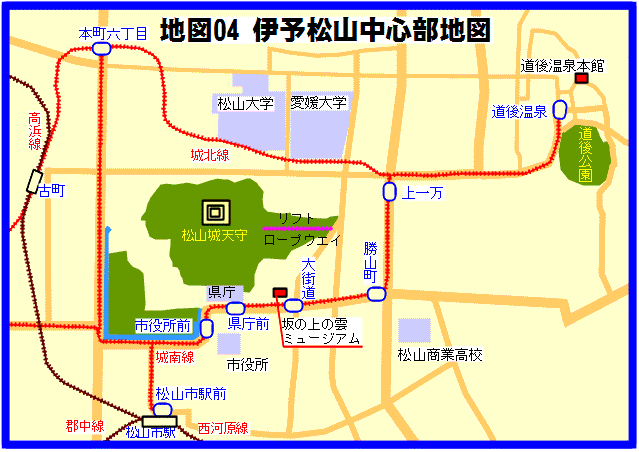|
この坂の上の雲ミュージアムは、いうまでもなく司馬遼太郎氏の同名の作品をもとに、松山市全体をフィールドミュージアムとする構想により、2007(平成19)年4月に開館しました。
つまり、司馬氏の『坂の上の雲ミュージアム』に描かれた松山出身の三人の主人公、正岡子規、秋山好古、秋山真之の軌跡に注目しつつ、司馬氏のメッセージを通して、明治国家という日本の近代国家建設がどういうものであったか、ひいては、今の日本がどうあるべきかを「哲学」するミュージアムとして構成されています。
おりからNHKにおける同名の番組の放映とも重なって、開館から僅か2年半後の2010年1月には40万人目の入場者を記録しました。今大人気の、松山の観光名所のミュージアムです。
ただし、展示物は、司馬遼太郎氏の文書やいろいろなメッセージ、3人の事跡の紹介などが中心で、はっきりいって、そういうことに興味のない人に、「すごい」と感じさせるものではありません。
司馬遼太郎にも歴史にもそれほど興味のない妻には、このミュージアムは、それほどには感動を与えませんでした。
妻は日本史教師の解説者付きで、辛抱して1時間余の館内周遊に耐えました。
|
私
|
「司馬遼太郎氏は君も知ってるように、いろいろな作品を残している。何か読んだものはある?」
|
|
妻
|
「あまりない。大河ドラマは面白かった。大昔の『国盗り物語』なんか。」
|
|
私
|
「『龍馬が行く』も有名だし、『街道を行く』シリーズもすごい。」
|
|
妻
|
「それはあまり知らない。」
|
|
私
|
「司馬氏が、どんな理由で歴史小説を書くようになったか知っているか?いいかえれば、彼の作家としてのテーマの根源が何か聞いたことはあるか?」
|
|
妻
|
「そんな難しいことは知らない。」
|
そうですね。そんなことは普通の方は知りません。
|
私
|
「司馬遼太郎氏は、第二次世界大戦が日本の敗戦で終わる1945(昭和20)年の8月には、戦車隊の小隊長として栃木県にいた。」
|
|
妻
|
「フィリピンとか満州とかじゃないの?」
|
|
私
|
「違う。満州や南の島にいたら、とても生き残るなんてできなかった。日本の戦車はアメリカやソ連の戦車には全くかなわないお粗末なものだったから。」
|
|
妻
|
「じゃ、日本にいてよかったわけじゃない。」
|
|
私
|
「そう、そうして生き残った司馬氏の心に強烈な疑問が起こった。簡単に言えば、『日本はなんてバカな戦争をしたんだろう。日本は昔からこんなバカな国だったのだろうか?』という疑問が。」
|
|
妻
|
「へー。」
|
これについては、司馬氏自らが次のように書いています。
|
「 私は、ノモンハン事件のことを調べてみたかったのです。ずいぶん調べました。資料も集めました。人にも会いました。会いましたけれども、一行も書いたことがないのです。それを書こうと思っていながら、いまだに書いたことがなくて、ついに書かずに終わるのではないか、そういう感じがします。
日本という国の森に、大正末年、昭和元年ぐらいから敗戦まで、魔法使いが杖をボンとたたいたのではないでしょうか。その森全体を魔法の森にしてしまった。発想された政策、戦略、あるいは国内の締めつけ、これらは全部変な、いびつなものでした。
この魔法はどこから釆たのでしょうか。魔法の森からノモンハンが現れ、中国侵略も現れ、太平洋戦争も現れた。世界中の国々を相手に戦争をするということになりました。
たとえば、戦国時代の織田信長(1534〜82)だったら考えもしないことですね。信長にはちやんとしたリアリズムがあります。自分でつくった国を大切にします。不利益になることはしません。
国というものを博打場の賭けの対象にするひとびとがいました。そういう滑稽な意味での勇ましい人間ほど、愛国者を気取っていた。そういうことがパターンになっていたのではないか。魔法の森の、魔法使いに魔法をかけられてしまったひとびとの心理だったのではないか。
私は長年、この魔法の森の謎を解く鍵をつくりたいと考えてきました。
たとえば、これをマルクス主義に当てはめれば、パッと一言でこれこれだということになるのかもしれませんが、それでは魔法の森の謎を解くことはできません。
手づくりの鍵で、この魔法の森を開けてみたいと思ってきたのです。どうも手づくりの鍵は四十年たってもできたのか、できていないのか −その元気があるのか、ないのか− とにかくその鍵を合わせて、ノモンハンについて書きたかったのですけれども。
あんなばかな戦争をやった人間が、不思議でならないのです。」
|
|
※
|
司馬遼太郎著『「昭和」という国家』(NHK出版 1998年)P5−6
|
|
私
|
「司馬氏は、いろいろ調べた結果、少なくとも明治国家を作った人々は、世界に誇りうる、立派な人間だったという結論にいたる。ついでにいえば、それをなさしめた要素は、江戸時代からの伝統であり、「武士道」であったと結論している。」
|
|
妻
|
「NHKのドラマの最初の部分にも出てくる、『坂の上の雲』のあの有名なセリフ。」
|
|
私
|
「そうそう。ほらこのパネルにも書いてある。『まことに小さな国が、開花期を迎えようとしている。・・・・』」
|
これについては、『坂の上の雲』に次のように表現されています。
|
「 余談ながら、私は日露戦争というものをこの物語のある時期から書こうとしている。
小さな。
といえば、明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう。産業といえば農業しかなく、人材といえば三吉年の読書階級であった旧士族しかなかった。この小さな、世界の片田舎のような国が、はじめてヨーロッパ文明と血みどろの対決をしたのが、日露戦争である。
その対決に、辛うじて勝った。その勝った収穫を後世の日本人は食いちらしたことになるが、とにかくこの当時の日本人たちは精一杯の智意と勇気と、そして幸運をすかさずつかんで操作する外交能力のかぎりをつくしてそこまで漕ぎつけた。いまからおもえば、ひやりとするほどの奇蹟といっていい。」
|
|
※
|
司馬遼太郎著『坂の上の雲1』(文春文庫 1999年)P77
|
また、別の本では次のように表現しています。
|
「 リアリズムといえば、明治は、リアリズムの時代でした。それも、透きとおった、格調の高い精神でささえられたリアリズムでした。ここでいっておきますが、高貴さをもたないリアリズム −私どもの日常の基礎なんですけれど−それは八百屋さんのリアリズムです。そういう要素も国家には必要なのですが、国家を成立させている、つまり国家を一つの建物とすれば、その基礎にあるものは、目に見えざるものです。圧搾空気といってもよろしいが、そういうものの上にのった上でのリアリズムのことです。このことは、何度目かに申しあげます。
そこへゆくと、昭和には −昭和二十年までですが −リアリズムがなかったのです。左右のイデオロギーが充満して国家や社会をふりまわしていた時代でした。どうみても明治とは、別国の観があり、べつの民族だったのではないかと思えるほどです。」
|
|
※
|
司馬遼太郎著『「明治」という国家』(NHK出版 文春文庫 1989年)P7
|
展示室をぐるっと回っていくと、ちゃんと最後の方に、さらにうんちくのある引用が展示されています。
|
妻
|
「日露戦争は頑張って勝利したのに、いつから日本はおかしくなったの?」
|
|
私
|
「司馬氏によれば、その日露戦争の「勝利」そのものがよくなかった。具体的には、戦争は「勝利」というより、薄氷を踏むぎりぎりの優勢勝ちでしかなかったのに、国民も多くの指導者も、「大勝利」と勘違いした。その逆の思い込みが、傲慢さや横柄さにつながっていく。そこのパネルを見てご覧。」
|
パネルには次の文章が引用してありました。小説そのものではなく、その「あとがき」からの引用です。
|
「 要するにロシアはみずからに敗けたところが多く、日本はそのすぐれた計画性と敵軍のそのような事情のためにきわどい勝利をひろいつづけたというのが、日露戦争であろう。 .
戦後の日本は、この冷厳な相対関係を国民に教えようとせず、国民もそれを知ろうとはしなかった。むしろ勝利を絶対化し、日本軍の神秘的強さを信仰するようになり、その部分において民族的に痴呆化した。日露戦争を境として日本人の国民的理性が大きく後退して狂躁の昭和期に入る。やがて国家と国民が狂いだして太平洋戦争をやってのけて敗北するのは、日露戦争後わずか四十年のちのことである。敗戦が国民に理性をあたえ、勝利が国民を狂気にするとすれば、長い民族の歴史からみれば、戦争の勝敗などというものはまことに不可思議なものである。 昭和四十四年十月」
|
|
※
|
司馬遼太郎著『坂の上の雲8』(文春文庫 1999年)P321−322 「あとがき2」より
|
観覧料400円で、たっぷりと「日本」を哲学できた1時間でした。
|