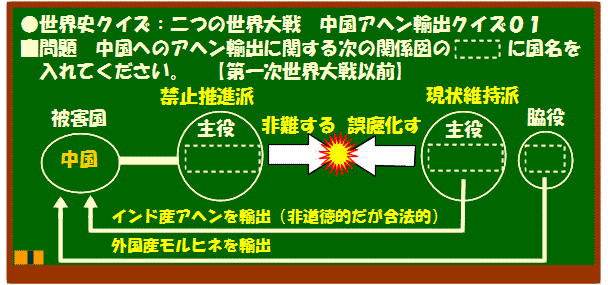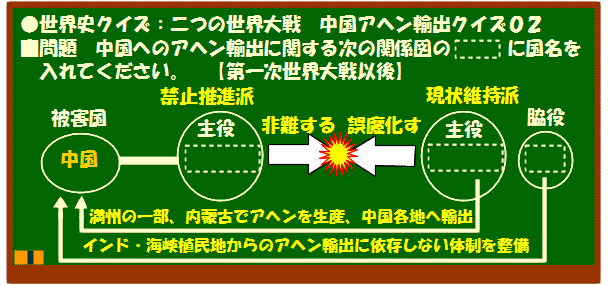|
では、今回の問題の本題に入ります。
まずは、19世紀の復習です。
【19世紀の二つの戦争】
イギリスが中国との貿易拡大や経済的な進出を狙って、二つの戦争、アヘン戦争とアロー戦争(第二次アヘン戦争)を起こしたのは周知の事実です。
アヘン戦争後の南京条約によって次の権利を手に入れました。
|
・香港島の割譲 ・上海・寧波・福州・厦門・広州の5港の開港 ・公行の廃止 ・賠償金の支払い
|
しかし、これによっても期待する貿易拡大がなされないわかると、イギリスはさらに、フランスに呼びかけて共同出兵し、2度目の戦争を起こします。これがアロー戦争です。
この結果、天津条約・北京条約が締結され、イギリスは次の権利を手に入れるとともに、アヘンの輸出を公認させました。
|
・外国公使の北京駐在 ・天津など11港の開港 ・外国人の中国内地での旅行の自由
・キリスト教不況の自由 ・九龍半島南部の割譲
|
これによって、イギリスのインド植民地から中国へのアヘンの輸出量は増加していきました。
アヘンを外国に売りさばいてそれで利益を上げるということは今日なら国際的に禁止されている事項ですが、当時のアヘンに対する認識は、現在のものとは少し異なっていました。
「 しかし一方で、注意すべき点も二つある。第一に、最初にも触れたように当時のイギリスでアヘンは広く使用されており、過剰に搾取すれば害があるとしても、それはアルコールなどほかの物も同様と考えられていたことである。とくにアヘンを食べることは、アヘンを精製した煙膏を吸うより害が少ないと考えられていた。また、アヘンを吸う場合には、他の物と混ぜずに良質な煙膏を用いる方が害は少ないと考えられ、インドで均質な生アヘンをつくるよう意を用いたのは、そのためであった。中国と戦火を交えるべきか否か議論された際のイギリス議会で、アヘンの害そのものに注目して反対したのが、「起源においてこれほど不当な戦争は聞いたことがない」との演説をおこなった、当時30歳のグラツドストンら少数派であったのも、当時のイギリスの状況からすればそれほど驚愕すべきことではなかったのである。
第二に、イギリスはアヘンを中国に売り込んだが、「商品」がアヘンである必要はなかった。売れて儲かるものでさえあれば、砂糖でも、コーヒーでも何でもよかったのである。そして、その商品を対等の立場で自由に取引できるようにすることが、十九世紀中葉のイギリス人の要求であった。
なぜ中国で他の商品でなくアヘンがそれほどよく売れたのかは、未だ解明できていない問題である。中国でのアヘン消費の特徴は、アヘンを吸うということであるが、この行為は、明末(十六世紀後半~十七世紀前半)にアメリカ大陸からタバコが台湾海峡付近に持ち込まれ、オランダ人がそれをアヘンと混ぜて用いたことから広まったという。そしてのちには、タバコを混ぜずに純粋のアヘンを煉膏に加工して吸うようになった。
アヘンを単に口に入れるのではなく長い煙管を使って吸うためには、準備の手間も費用もかかった。ジェンらの研究によれば、アヘン吸煙は明代には有産階級がくつろぐためにおこなったものだったという。このレベルでは、アヘンを消費する理由は主として緊張を解きほぐすため、くつろぐためであったと考えられる。また、ともにくつろぐ社交の手段としても用いられるようになっていった。アヘンを吸っても飲酒と違って顔が赤くなるなどの外見的変化が現れず、暴力や粗野な行動を引き起こすこともなかったために好まれたという。さらに、アヘンの吸煙は、中国上流階級の楽しみや社交の手段だけに留まらず、上流の生活に憧れる者も彼らを模倣して吸煙を始めることとなった。」
※参考文献4 後藤春美著『アヘンとイギリス帝国』P10-11
|