クイズ日本史 太平洋戦争期
| 太平洋戦争期7 |
| | 前の時代の問題へ | 太平洋戦争期の問題TOPへ | 次の時代の問題へ | |
| <解説編> |
| 913 オーストラリアの高校の教科書に記載されている「ココダ」とは、どこの島の地名でしょうか? 12/11/12記述 | |||||||||||||||
|
全体のボリュームが大きくなりますから、次の順序で説明します。
|
最初に、私がこのクイズ(と同時に目から鱗の話)を発想できた理由を説明します。
これがこのページをつくるきっかけとなりました。 |
|参考文献一覧へ|
正解は、ニューギニア島です。ニューギニア島は、先の大戦時にはオーストラリアの委任統治領(実質的には植民地)であり、現在は独立して東半分はパプアニューギニア、西半分はインドネシア領となっている島です。 |
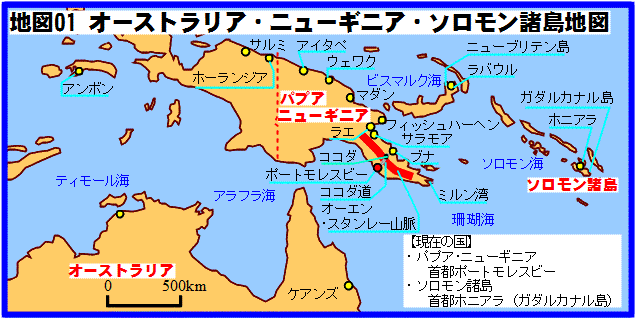
|地図3 太平洋戦争要図へ||攻略作戦年表へ|
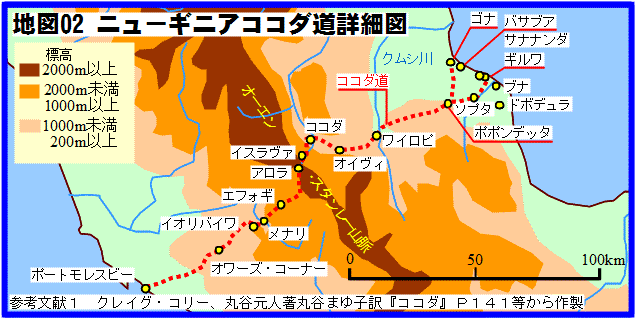
|
地図2をご覧になればわかりますが、道といっても、平地は深い森林や沼地のある熱帯のジャングルを通過し、オーエン・スタンレー山脈に入ると1000m以上の峰をいくつも超え、標高の一番高いところは2000mを越える地点を通過するというくルートです。道というよりは、その半分以上は登山道というべきです。 |
日本軍はなぜニューギニア戦を戦うことになったのでしょうか? |
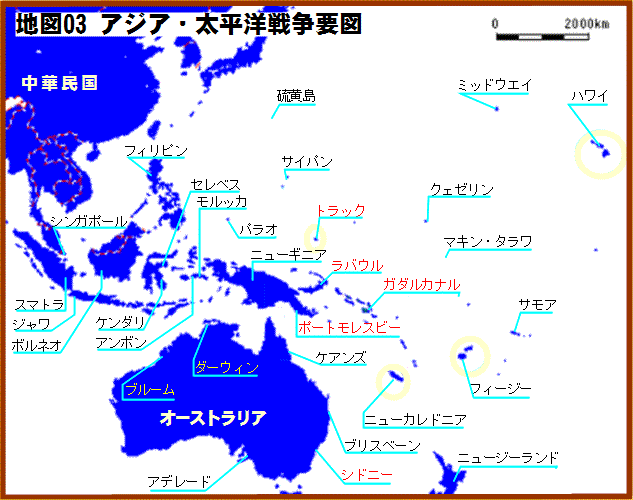
|地図1 ニューギニア全体図へ||地図2 ココダ道詳細図へ||攻略作戦年表へ| |参考文献一覧へ|
|
東京からニューギニアのポートモレスビーまでは、直線距離で5000km程あります。
この基地のうち最大のものがこそが、カロリン諸島のトラック諸島でした。トラック諸島は、第一次世界大戦時の旧ドイツ領で、戦後国際連盟の委任統治領として、実質的に日本が植民地支配を続けていた島です。現在は、ミクロネシア連邦のチューク州となっています。 |
日本軍のポートモレスビー攻略作戦の経過と、撤退後のブナ地区の戦闘の経過は、次の年表のとおりです。 |
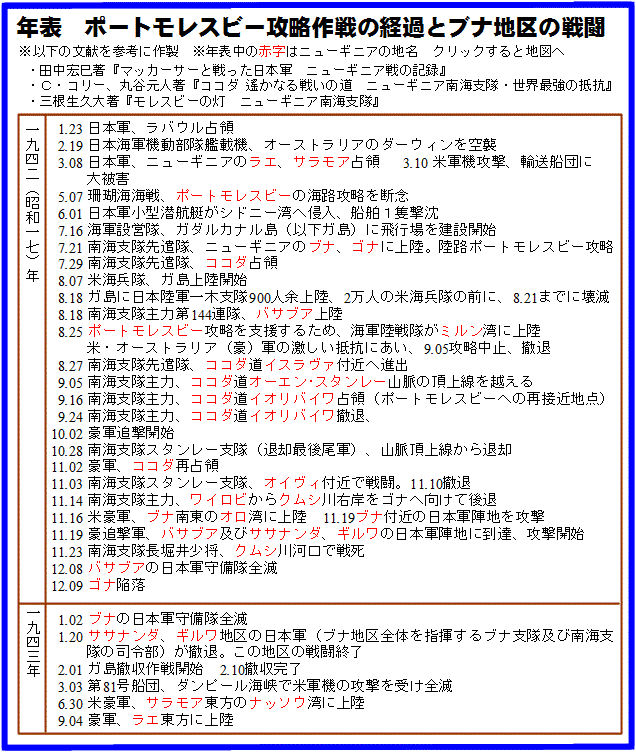
|
ニューギニアの制圧においては、東部の米豪軍の戦略的拠点であり、大規模な航空基地のあるポートモレスビーの攻略こそが第一の目標となりました。
結果的に、この心配が現実のものになりました。 |
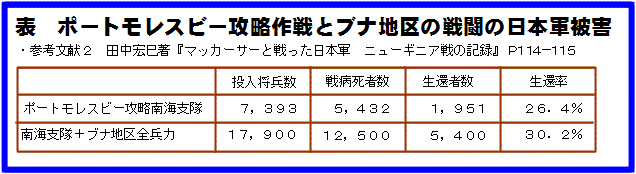
|地図1 ニューギニア全体図へ||地図2 ココダ道詳細図へ||地図3 太平洋戦争要図へ||攻略作戦年表へ|
|参考文献一覧へ|
ポートモレスビー攻略戦は、上記のように、日本軍からみれば、より有名なガダルカナル島の戦いと同じく、攻勢終末点を超えて進軍をしたために補給線に破綻をきたし、消耗戦の結果敗北に至った戦いでした。 |
 |
 |
資料913-01 |
|
P134の主な記述です。(赤字は引用者が施しました。) |
|
オーストラリアの人口は、現在では2200万人を越えていますが、1941年当時は、移民制限をして白豪主義(白人中心政策)を掲げており、人口も700万人程の小国でした。
|
|参考文献一覧へ|
|
そのように警戒している矢先、シンガポール陥落から4日後の2月19日に、オーストラリア北部のダーウィンが日本軍海軍機の大空襲を受けます。
|
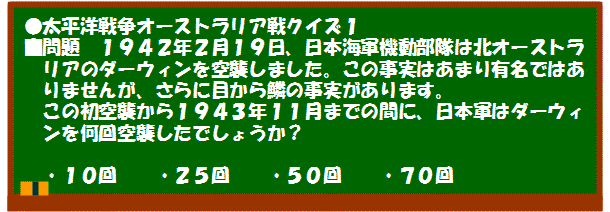 |
| ※例によって、黒板をクリックしてください。答が現れます。 |
| ※参考文献6 越田稜編前掲書 P315 |
|
日本軍のこの執拗な空襲の回数が、逆にオーストラリアの感じていた「危機感」の強さと考えてよさそうです。 |
|
1942年前半の時期は、オーストラリアにとって次ふたつの意味で大切な時期となりました。 |
ここで、また原点に戻って、オーストラリアの歴史の教科書『Retroactive 2』を見てみましょう。 |
 |
 |
資料913-02 |
|
P136・137の主な記述(赤字は引用者が施しました。)
これで、このページの冒頭のALTのN氏の発言、「ココダトレイルはトレッキングの場所として人気を集めている」の意味がご理解いただけたと思います。 |
これまで見てきたようなオーストラリア側の高い注目度に対して、日本側から見た太平洋戦争におけるニューギニア戦についても、再評価の必要性が提唱されています。どういうことでしょうか? |
|
これに対して、これまでの太平洋戦争の見方を変え、ニューギニア戦やオーストラリアとの戦闘の意義を重視すべきだと主張しているのが、参考文献2の田中宏巳著『マッカーサーと戦った日本軍 ニューギニア戦の記録』です。 |
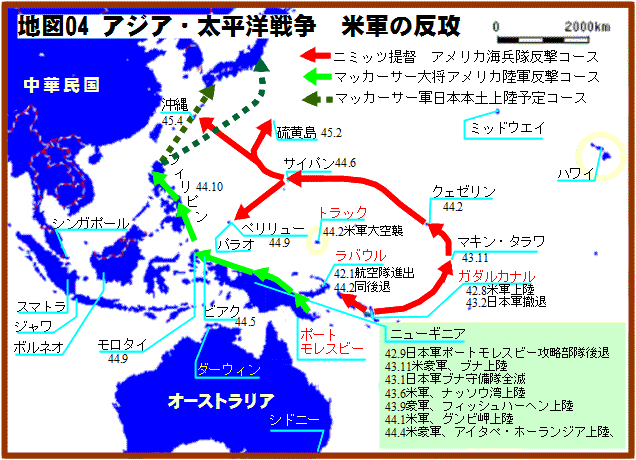
|地図1 ニューギニア全体図へ||地図2 ココダ道詳細図へ||地図3 太平洋戦争要図へ||攻略作戦年表へ|
|
ガダルカナル島の戦いがアメリカの勝利に終わった時点で、アメリカ海軍は、戦争の今後の帰趨を左右する決定的な力を手にし始めていました。アメリカ軍機動部隊において、エセックス級の航空母艦の一番艦、空母エセックスが就役し1943年1月にハワイに到着したのです。これ以後、エセックス級航空母艦が次々と就役し、新しい機動部隊の編成と訓練が着々と進んでいきます。
|
 |
|
写真913-03 ウェワク近郊のダグアの日本軍基地を爆撃するアメリカ軍機 (撮影日 1944/02/03) |
|
この写真は、ロバート・シャーロッド編中野五郎訳『光文社版 記録写真 太平洋戦争史(下)』P23から複写しました。 |
|
ニューギニア戦は、全体として南西太平洋方面司令官マッカーサー大将によって指揮されていましたが、最初はオーストラリア軍との戦いで始められ、、1944年1月のグンビ岬上陸以降はアメリカ軍が中心となり、また、アメリカ軍がフィリピンに去ってからは、終戦まで再びオーストラリア軍との間で進められました。 |
|
3年あまりのニューギニア戦に総合計でいくらの兵力が投入され、何人の日本人将兵が熱帯の地に倒れたのか正確な数字を出すことは不可能です。田中宏巳氏は、次のように推定しています。
犠牲者の中に、食糧不足による飢餓やマラリアなどの病気によってなくなられた方がかなりの数含まれていることは、一つ一つ具体的に説明しなくても、最初の南海支隊の例から考えてみれば、おわかりいただけると思います。 |
|
ずいぶん長くなりましたが、これでニューギニア戦に関するレポートを終わります。 |
|
※上の地図は、Google から正式にAPIキーを取得して挿入した、ニューギニアの地図です。 |
|
【クイズ913 ニューギニアにおけるオーストラリアと日本の戦い 参考文献一覧】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||