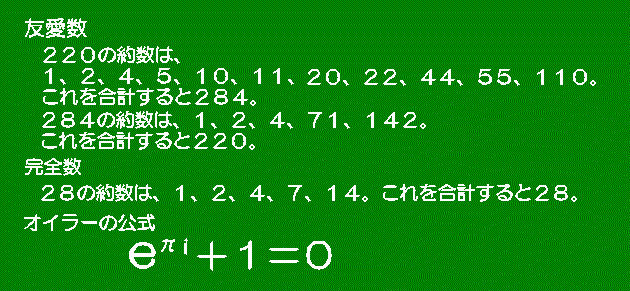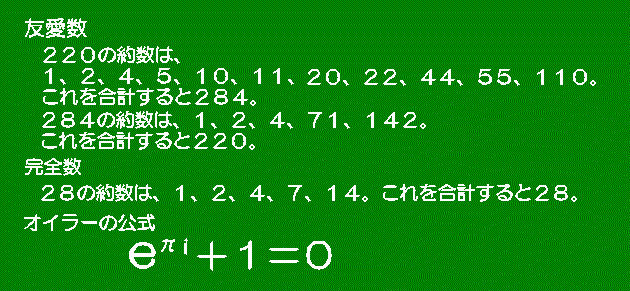2006年最初の日記です。
このところ、新しい年がはじまると、日記にその時点での自分の考えや大切にしたいことを書いてきました。
ところが、今年は、いきなり、「戦艦大和」シリーズ(まだお読みでない方は、こちらです。 )へ突入してしまい、そのチャンスを失ってしまっていました。 )へ突入してしまい、そのチャンスを失ってしまっていました。
そこで、この映画鑑賞記にかこつけて、現在やこれからの思いを書こうと思っています。
今日、映画「博士の愛した数式」を見てきました。
ちょうど1年前、腸閉塞で入院中(入院記はこちらです。 )に原作(小川洋子著『博士の愛した数式』(新潮社文庫 2003年)を読み、なかなか渋いいい作品だと思っていました。 )に原作(小川洋子著『博士の愛した数式』(新潮社文庫 2003年)を読み、なかなか渋いいい作品だと思っていました。
私だけがいいと思ったのではなく、この原作は、2004年度から設けられた「本屋大賞」の第1回受賞作品です。また、読売文学賞を受賞し、キノベス2003(紀伊国屋書店スタッフが自分で読んでみて面白いと思った本)第1位にも輝いています。
いわば、本としては高い評価を受けた作品です。
その原作をもとに、作られたのがこの映画です。
まず、わが家の映画評を示します。今回は、息子たちは参加できず、妻と二人だけでした。
| お薦め人 |
お薦め度
(3点満点) |
コ メ ン ト |
| 私 |
★ ★ ★ |
限られた時と永遠の時間、生きるということの意味を考えさせられる映画です。 |
| 妻N |
★ ★ ★ |
心と心が一つ一つつながっていくことが嬉しくて、そして悲しくて、涙涙の映画です。 |
| 次男Y(19歳) |
−−− |
試験前で欠席 (-.-) |
| 3男D(15歳) |
−−− |
部活で忙しく欠席 (-.-) |
|
※「博士の愛した数式」の公式サイトはこちらです。
俗に、原作の評判が高いと、映画は、評判倒れに終わってしまうということがよくありますが、この映画については、上記のように、原作同様、お薦め度が高い作品になったと思いました。
小説のストーリーをかいつまんでお話をします。
主人公の「私」は家政婦です。18歳の時から10年間続けているベテランですが、今回紹介されて向かった先は、ちょっと変わった人物の家でした。そこの住人、「博士」は大層な数学の研究家でしたが、普通の人間ではなかったのです。
「博士」は、自動車事故で脳に障害をもってしまい、事故以前の記憶は完璧であるにもかかわらず、現在の記憶は、80分しかもたない人だったからです。つまり、エンドレスのテープのように、80分過ぎると、記憶はリセットされてしまうのです。
「私」は、「博士」の命令でその家に立ち寄るようになった自分の息子、「博士」が「√(ルート)」と名付けた小学校5年生の10歳の息子と2人で、日常生活の中で、この奇妙な「博士」から、数学のもつ、数字のもついろいろな魅力を教えられます。
「博士」の義理の姉との関係、タイガースの江夏豊投手の話など、数学以外の要素も絡み合って物語は展開ししていきます。
「私」と「√」は、数字の神秘性と永遠性に魅了されながら、「博士」の限られた記憶(=限られた時間)と接する中で、時間が過ぎていくことの意味、限られた時間と永遠の時間の違いや、壊れていくもの壊れずに残っていくものの違いに、気付づいていきます。
映画は、いつもながら短い時間の制約を受けるため、原作小説ほどには、登場人物の4人「私」「息子」「博士」「義理の姉」の心情を、十分には描ききっていません。「私」の出生の秘密、「息子」の出生の秘密は、映画では語られていません。
しかし、それを補ってあまりある2つの素晴らしい点が、この映画のお薦め度を高めました。
その一つは、物語の舞台として、信州を選びその自然を背景に使ったことです。この物語には、特定の町は必要ありません。「私」と「博士」が出会う場所は、地方の都市ならどこでもいいのです。
この映画の監督の小泉堯史さんは、この映画の心を描く舞台として、あえて早春から初夏にかけての信州の自然を選びました。これが正解でした。監督自身も、インターネットのオフィシャルサイトの中で、「お互いの話し言葉の中に、暖かい春の萌しを、感じ取っていただけたら」とメッセージを送っていますが、それと早春から初夏の信州の自然は、見事にマッチしました。
2つ目に、舞台設定以上に見事だったのは、小説と異なる主人公を設定したことです。
小説は、「私」、つまり、「√」の母=家政婦が主役で、「私」という一人称で登場します。
しかし、映画では、息子の「√」が主人公になっています。
原作では、「√」は、「博士」との交流で感化を受け、大学4年生の時に、数学の先生の教員採用試験に合格し、それを「博士」に報告したところで終わっています。
映画では、その「√」が、中学校の29歳の数学の先生として、1年の最初の授業にあたる4月の第1回目の授業で、自己紹介をかねて数学の魅力を語るところからはじまります。
そして、映画は、その後も一貫して、教室で生徒相手に説明を続ける「√」の話として、進行します。もちろん、「√」にとっては、19年前の思い出となる、「博士」との日々が映像で再現されるという寸法です。
ところで、この、最初の授業で、数学の魅力を語るという設定が、また、監督の見事なオリジナリティーとなりました。
このことにこんなに魅了されてのは、もちろん、私が教師であるからこそです。会社員や自営業の方には、以下に書くような思い入れは理解しがたいことになるのかもしれませんが、ご容赦願います。
「√」の役の吉岡秀隆さんを演技を見ていて、自分の若かりし日を思い出しました。
ちなみに、数学教師「√」は、29歳の設定になっていますから、教師としてはまだまだ未熟で、そのあたりは監督の演技指導と、吉岡さんのキャラクターがうまくかみ合って、実にうまく表現されています。
つまり、自信満々と言うよりは、どこか弱々しく、しゃべり方・黒板への文字の書き方、どれをとっても、まだ未熟者の教師のそれになっています。
朗々とした、生徒魅了するしゃべりではありません。
しかし、話し方は木訥でも、自分にまず語る夢があって、生徒を引きつける夢があって、それを1年間一緒に勉強していこうという、そう言う若々しい教師の語りです。
階乗、素数、友愛数(220と284という二つの数字のの関係は、220の約数の一つ一つの合計が284になり、284の約数の一つ一つの合計は220になるという運命的な絆関係にある。)、完全数(28の約数を合計すると28になる。)、そして、オイラーの公式。 |