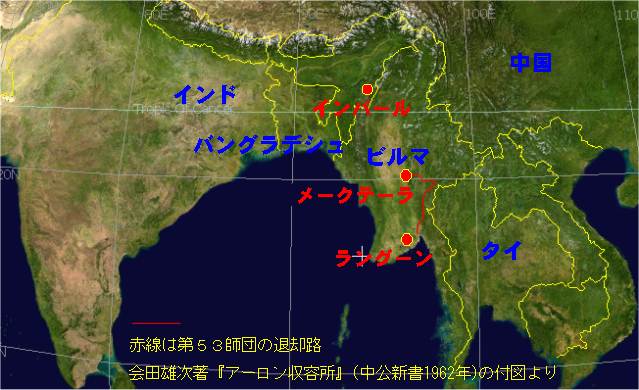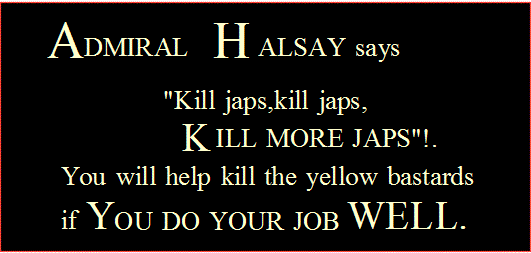|
上述のプロパガンダに加え、日本への反抗を進めるアメリカ軍の指揮官たちの「士気を鼓舞する」言動も、日本人への差別感を具体的に表したものでした。
その代表例が、ウィリアム・ハルゼー提督の次の行為です。
提督は、ガダルカナル島の攻防戦に勝利したあと、ソロモン群島において反攻線を開始する際、同群島のツラギ島(ガダルカナル島の対岸、アメリカ軍海軍基地がある島)に次の看板を掲げさせました。
| 【追加記述】 以下の引用は、2010年6月20日に追加記述しました。 |
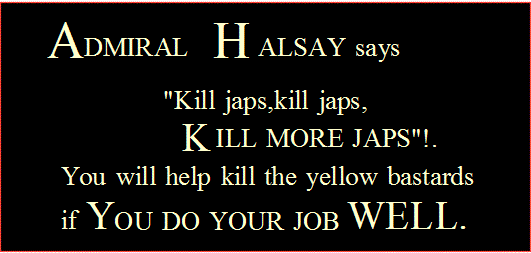 |
| ※ |
上の文言は、次の書物から引用(復原)しました。当初この文言がどういう形で流布していったのか分かりませんでしたが、同書に詳しく説明してあります。
エヴァン・トーマス著 平賀秀明訳 『レイテ沖海戦 1944 日米四人の指揮官と艦隊決戦』(白水社 2008年)
|
ヨーロッパ戦線においては、アメリカの主たる敵はドイツ軍でしたが、ドイツ民族に対しては、アメリカは日本人に示すようなむき出しの敵意と差別感は示しませんでした。
ジョン・W・ダウアーは次のように指摘しています。
|
「第一の、暴虐のかぎりをつくしたドイツ人以上に日本人が憎悪の対象となったのはなぜかという問いに対する答えが、人種的要因に負うところが多いのは確かであるが、それは見た目よりはもっと複雑な背景をもっている。ドイツ人の残虐行為は古くから知られ非難されていたが、そうした中でも、良いドイツ人と悪いドイツ人は明確に区別されており、連合国側は残虐行為を「ナチス」犯罪と称し、ドイツ文化や国民性に根ざす行為とは見なさなかった。それ自体は合理的姿勢であったといえるだろうが、首尾一貫していたわけではなかった。というのは、アジアの戦場における敵の残虐行為は常に、単に「日本人」 の行為として伝えられたのである。」 |
|
※
|
ジョン・W・ダウアー前掲著『容赦なき戦争 太平洋戦争における人種差別』P83 |
また、同じヨーロッパ戦線でも、陸上よりも相手に対する敵愾心をあおられることが少ない海軍の戦いでは、陸上戦闘以上にフェアな戦いが行われていました。
かの有名なドイツ戦艦ビスマルクは、1941年5月27日、イギリス艦隊の包囲網の中で絶望的な戦闘の果てに、単艦撃沈されました。もちろん、生存者を助けるドイツ艦船は存在しません。
しかし、2200名のビスマルク乗員のうち、5%にあたる110名が、イギリス艦隊の数隻に艦船に助けられ、捕虜としての厚遇を受けています。
|
※ |
ブルカルト・フォン・ミュレンハイム著佐和誠訳『巨大戦艦ビスマルク』(早川書房 1994年)P322 |
|