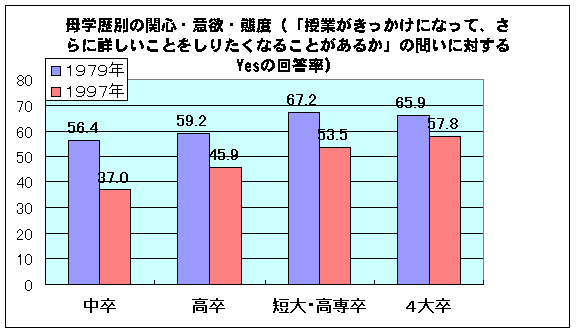学力をめぐる論争のひとつに、教育社会学者の立場からの、考慮に値する意見があります。
それは、「社会階層間の学力格差」です。
そもそも日本は、ヨーロッパ諸国に比べて、社会的流動性が高いといわれてきました。
つまり、近代工業社会の形成が欧米より遅れた日本では、その形成と教育の普及が同時期に展開し、それによって、近代以前にどんな階層の出身でも、高い教育さえ受けることができれば、一般のホワイトカラーを初めとして弁護士や医者など、いわゆる社会の中の管理的職種に就けることができる社会だったのです。
これに対して19世紀から労働者階級の形成が行われたイギリスやフランスなどでは、教育という装置が普及する前に社会階層が形成されてしまい、その結果、近現代においても、社会的上層と下層との流動性は顕著には見られないという状況ができあがりました。
「教育が高い地位を約束するという」事実と、機会均等を大原則とした教育制度と、比較的安価だった教育コストは、戦後の高度経済成長期にも、多くの国民の「上昇志向」を促す結果になりました。教育には、子どもの将来の夢を託すものがあったのです。
ところが、現在では、この装置と仕組みに変質が起きているというのが、冒頭の「社会階層間の学力格差」論です。
この論争の主役は、東京大学の社会学者苅谷剛彦教授です。
苅谷教授は、その著『階層化日本と教育危機』(有信堂2001年)で、実証的なデータにもとづいて、現在の教育政策の展開は、社会階層間の学力格差を広げる方向に進んでいると主張しています。
以下は、その主張の要約です。(膨大な論証のほんの一部です。)
苅谷教授は、まず、日本のこれまでの社会でも、実質的に、教育のレベルの階層間格差はあったといっています。例えば、東京大学の学生の親の年収は、どこの大学の親の年収よりも高く、実質的に受験競争を勝ち抜いて学歴やブランド大学卒の経歴を手に入れるのには、親の階層が大きな要素だった述べています。
日本における教育をめぐる論争では、そのことが敢えて問題にされなかっただけであるというのです。そういう差別を問題視するよりも、「誰でもがんばればなんとかなる」という努力主義が必要以上に強調されてきたのです。
教授は、現状について分析します。
①学習に向けての努力(学習時間)は減っているか?
②出身階層によって努力の量(学習時間)には差があるか?
③出身階層による努力(学習時間)の差は拡大しているか?
という三つの仮説を立て、それぞれデータによってそれを立証します。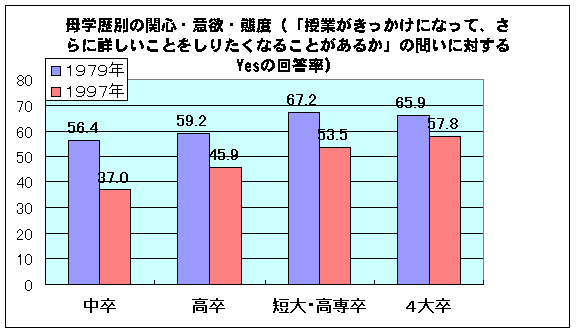
また、高校生の関心・意欲・態度を、「授業がきっかけになって、さらに詳しいことを知りたくなたことがあるか」という問いによって把握し、その回答が、親の階層、とくに母親の学歴によって大きく違い、それが、1979年度と1997年度では決定的に広がっていることを指摘しています。(上のグラフは、前掲書P182)
教授は、このような格差の拡大を「学習からおりてしまった子どもたち」と表現しています。こういう子どもたちが、1980年代以来のこれまでの教育改革で既に出現してしまったことに危機感を示し、新学習指導要領のもとで教育改革が進んでいけば、もっと深刻な事態に陥ると指摘しています。
なぜなら、このことこそが、新学習指導要領の目標とする「自ら学び自ら考える、生きる力」の育むことの困難さを明確に示しているからです。
教授は、この問題点を、インセンティブ・デバイドと表現しています。デジタル・デバイドといえば、「ITの技能に関する格差」ということですが、この場合は、インセンティブ(誘因・意欲)の格差です。
私たちは、どうしたらインセンティブ・デバイドを解消の方向へ進めることができるでしょうか?
また、苅谷教授は、つい最近では、『論座』6月号(朝日新聞社2002年)の、共同研究による学力調査の結果報告の第2回目として、「教育の階層差をいかに克服するか」の発表しました。保護者の文化的階層差による学力や学習意欲の格差について、次のように言っています。
つまり、小さい頃から子どもへの教育的投資(保護者が面倒を見る、習い事などにいかせるなどすべてにおいて)が比較的少なかった「文化的階層が低い」家庭の子どもは、学校では、むしろ基礎的基本的内容を教えてもらうことを望んでいるということなのです。
苅谷さんは言います。
「基礎的学習をおろそかにしたまま、はやりの学習を追うばかりでは、そのしわ寄せは恵まれない家庭の子どもに集まる。」
ここで、苅谷教授は、望むべき学校の在り方について提案を行っています。
調査対象校ごとの比較で、「ゆとり教育」以前とあまり学力が変化していない学校(調査した学校の多くは、1989年と2001年と比較では、学力の低下が見られた)を分析したところ次の特色が見られたのです。
「学習意欲」や「自主学習」をキーワードとする指導
「個別学習・少人数学習・一斉指導」の柔軟な組み合わせ
わからないときに「分からない」といえる学習環境
総合的な学習の時間で「連帯」「生き方」を重視し、学習の動機付けをしている
などです。苅谷さんはこういう学校を、「がんばっている学校」と表現しています。
ここでいう「がんばっている学校」とは、もちろん今までの伝統的な学校ではなく、かといって新学力観一辺倒でもなく、その両方の長所を組み合わせた学校なのです。
苅谷さんは、このような学校を増やすために、経済的に不利な子どもが多い学校に人的、財政的な支援を増やすなど、地域の実情に応じた教育を可能にするための基盤整備が必要だと、進言しています。
本県の教育改革を示すキーワードは、「個性と責任」、そして、競争原理です。
これは、何も本県独自のものではなく、今日本国中で進められている教育改革のルーツの時代から主張をそのまま受けついだものです。
現在の教育改革のルーツとは、あの中曽根内閣(1982年から87年)の臨時教育審議会の答申にあります。その中に、21世紀につながる教育改革として、「個性」の重視、競争原理」などがうたわれています。
中曽根首相の政治思想は、当時のアメリカ大統領レーガン、イギリス首相サッチャーと同じく、政治的には新保守主義、経済・社会的には新自由主義に基づくものでした。
新保守主義・新自由主義の特色の大きな一つは、規制緩和・自由競争の拡大でしたから、教育に対しても、その路線が進められて今日に至っていることには、何ら不思議な点はありません。
しかし、本来の自由で、社会的流動性が高いことが社会の活性化を促すのであるとするなら、苅谷教授が指摘する「社会階層間学力格差」の拡大は、重要な問題と言わなければなりません。
もともとの教育改革の路線が間違っていて大幅修正が必要なのか、あるいは、実践の仕方と支援の方法が不十分なのか?。
現場にいる我々としては、何かを盲信するのではなく、常にいろいろな角度から確かめながら進んでいく以外に、最良の方法はないと思いますが、いかがでしょう。 |