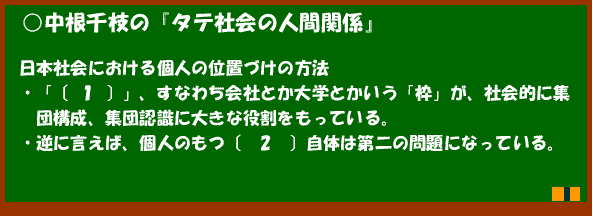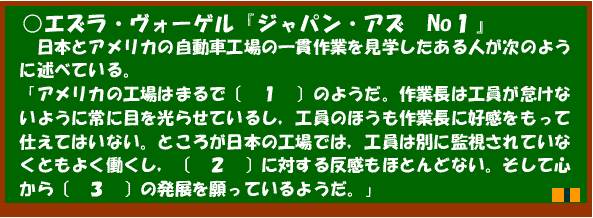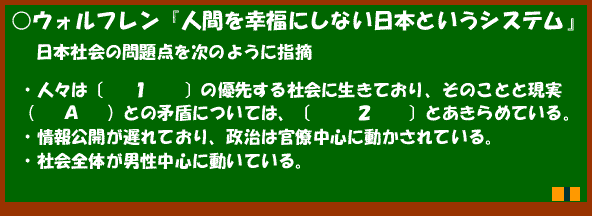|
日本経済の急成長は、ヴォーゲルのような日本再評価の動きと同時に、日本バッシングも惹起しました。すなわち、「欧米企業がいくら日本企業の成功要因をまねをしても、貿易赤字は減らない。これはやはり、日本社会の閉鎖性・異質性によるものではないか。」という批判的な考え台頭したのです。つまり、1980年代後半には、日本版経済への疑問と批判的再評価の動きが具体化してきました。
その動きは、バブル経済の破綻とともに、より顕著となります。
1990年代の日本経済の状況を文化批評家のマークス寿子さんは、『とんでもない母親と情けない男の国日本』の中で次のように説明しています。
|
「 いまさかんに「第二の敗戦」という言葉が言われている。この言葉にはいくつかちがった解釈があるが、ふつうはつぎのような意味で使われている。太平洋戦争でアメリカ(正しくは連合国軍であるが)に負け、アメリカに占領され支配をうけ、アメリカの指示に従って日本が復興したというのが第一の敗戦である。そして、日本が独立し、奇跡的ともいわれた経済成長を遂げ、アメリカとの経済戦争に勝ったょうにみえたが、バブル経済の崩壊とそれにつづく不況にともなって、「グローバル・スタンダード」などの主張のもとにふたたびアメリカの支配をうけるようになった、これをふつう第二の敗戦と言っている。
|
日本に対する批判的再評価を行った一群の人々は、リビジョニストと呼ばれました。「revisionist」(再評価論者)というネーミングは、1986年にオランダ生まれのジャーナリスト(この時点で日本滞在歴24年)のカルヴァン・ウォルフレンが、アメリカの外交誌『Foreign Affairs 』に「The Japan Problem 」という論文を発表して華々しく登場してから用いられるようになりました。
その後、彼は、クライド・プレストヴィッツ、チャーマーズ・ジョンソン、ジェームス・ファローズらとともに、リビジョニストの代表的人物となりました。
リビジョニストがどのような考え方であるのか?
たとえば、ウォルフレンは次のように述べています。
| ※ |
カルヴァン・ウォルフレン著『人間を幸福にしない日本というシステム』(毎日新聞社 1994年)P24−26 (赤字と行間設定は引用者が施しました。)
この「敵意」に満ちた本の題名が、そもそもリビジョニストの姿勢の基本を示しているようです。
|
|
「 日本人が完全に市民として行動するのは難しい。それは、市民として必要な知識の多くを奪われているからだ。日本という国が官僚と経済団体の役員たちによって実際にどのように運営されているか、その内幕は〔 1 〕という見せかけの奥に隠されている。日本の市民たちの明日の生活、さらにはその先々の生活にまで影響する最も重要な決定でも、通常は公に議論されることがない。「バブル経済」の発生と終息への大蔵省の関与は、その最も顕著な例だ。
日本の人たちは官僚からしばしば荒唐無稽のでたらめな話をきかされる。これは、官僚が面子を守りたいと思っていたり、正確な情報が世間に流れると実現のチャンスがまったくなくなるような計画を強行したいと思っていたりするからだ。
おまけに、日本のたいていの新聞は、新聞の第一の使命は市民に情報を提供することだなどとは思っていない。だから新聞は、「純朴」だが政治的には無知な日本人の層を存続させるのに手を貸している。メディアは、日本では、政治・経済・生活上の〔 1 〕という表向きのリアリティを「管理」するための、つゆ払いの役目を果たしている。
この管理されたリアリティは、われわれが努力すれば発見できる本当のリアリティと、たいへんちがっている。なるほど説明と実際の不一致は、すべての民主国家を含め、どの国にもある。しかし、私がここで指摘している日本のその落差は、他の先進工業国より、はるかに、はるかに大きいのだ。
日本の市民はたいてい、何かにつけ、このリアリティにはまり込んで動けなくなっていると感じている。表向きのリアリティが、管理されたつくりものに過ぎない、と時々は気づくが、結局はそれを受け入れざるをえない。なぜなら、周りの世界はすべてそれによって動いているからだ。日本人がこうした状況にはまり込んだ時、口をついて出るセリフが「〔 2 〕」である。
「〔 2 〕」というのは、ある政治的主張の表明だ。おそらくほとんどの日本の人はこんなふうに考えたことはないだろう。しかし、この言葉の使われ方には、確かに重大な政治的意味がある。「〔 2 〕」と言うたびに、あなたは、あなたが口にしている変革の試みは何であれすべて失敗に終わる、と言っている。つまりあなたは、変革をもたらそうとする試みはいっさい実を結ばないと考えたはうがいいと、他人に勧めている。「この状況は正しくない、しかし受け入れざるをえない」と思うたびに「〔 2 〕 」と言う人は、政治的な無力感を社会に広めていることになる。本当は信じていないのに、信じたふりをしてあるルールに従わねばならない、という時、人はまさにこういう立場に立たされる。
「〔 2 〕」という言葉を知るずっと以前、私が日本に来てまだ数カ月のころ、日本人のおとなしさ(=御しやすさ)には面くらったものだった。日本人は日常生活で必要以上の我慢を強いられているように見えた。ほかの先進国ではまず受け入れられるとは思えない生活条件を押しつけられていたからだ。
よく通った中間階級向けの食堂で、いつも出される食事のまずさと量の少なさには驚きっぱなしだった。喫茶店で、ソフトドリンクを一びん注文したつもりなのに、びんからはちょつぴり注いだだけで、はとんどは氷で埋まったグラスが出された時は、さすがに怒ったものだ。当時の外国人仲間で、それぞれが目撃した、ひどい扱いをされても何も文句を言わない日本人の驚くべき実例を、あれこれと話題にしたものである。私たちは、顔を合わせれば、日本人の「受け身で受け入れる」態度について語り合っていた。
後になって、この態度には自尊心がからんでいるとわかってきた。いちいち騒ぎ立てないのが大人の態度であり、私たち外国人のように文句ばかり言っているのは、子供じみていて自分勝手で、やっかい者の最たるものだと考えられているのが次第にわかってきた。成熟した大人の日本人なら、ひどい扱いもこれを許し、静かに耐えることによって、互いを安け入れ合うというわけだ。
日本には昔から、仕方がないと言えるようになれば成熟した証拠だとみなす伝統がある。そして確かに、これは日本だけの伝統ではない。西洋でも、いや世界中どこでも、自分の能力の限界の自覚が、もはや子供ではない証拠だ。しかし、重要なちがいもある。私と友人が初めて日本にきた当時、私たち外国人は、こんな詐欺まがいの商慣行を顧客として中止させる能力が自分たちにないなどと、どうしても容認できなかった。食堂や喫茶店のはかの客も私たちの抗議に加わってくれれば、イカサマ商売はやめさせられるというのが私たちの考え方だったのだ。
日本の市民の生活環境としては不幸なことに、徳川時代の全体主義的な政治体制が、今日もまだ幅を利かせているのである。日本が市民の国となるためには障害になるに決まっている生き方が、いまだに正しいとされている。
徳川時代なら、「〔 2 〕」や、それに類する当時使われた言い方は、とても理に適っていただろう。なにしろあの時代には、庶民は国のいたるところで、ひどい政治に耐えなければならなかった。
自分の人生をより自由に生きたいと思う市民は、「〔 2 〕」という一句を自分の辞書から追放した方がいい。しかし、そうするためには、まず勇気が必要だ。本書が励ましになってほしいと思う。 |
アメリカの工場と日本のそれとの違いを、次のように説明しています。
※答えが決まったら黒板をクリックしてください。正解が現れます。(黒板一枚分、一度に全部現れます。)
これらリビジョニストの指摘は、ある面では日本社会の課題を鋭く指摘しているといえるでしょう。
しかし、その発想や視点に問題も感じます。
リビジョニスト自身の問題について、浜口恵俊(出版当時、国際日本文化研究センター教授)教授は、「日本研究の新たなるパラダイム」で次のように説明しています。
※梅原猛編著『日本とは何なのか』NHKブックス、1990年9月)所収
|
昨今大きな話題となったものに日米構造協議(アメリカ側はStructura Impediments lnitiative と呼ぶ)がある。またその前には、日米貿易摩擦をめぐつて、包括貿易法スーパー301条による報復措置の発動問題があった。そこでは、アメリカ側はかなりの危機感を抱いて、日本の社会=経済の構造の変革を要請してきた。日本人の貯蓄体質、排他的なビジネス慣行、経済取引の系列化など、日本文化と結びついたビジネス特性を姐上にのせて厳しく批判し、その改善を要望したわけである。もっとも、日本が実際に同意したのは、公共投資の増額、大規模小売店法の見直しなどであり、政策面での改善にとどまった。
だがこうした構造協議などにおいて、アメリカ側の主張の背後に見え隠れしている一つの見解が
ある。それは、リビジョニスト (日本についてのこれまでの通説的な見方を変えようとする論者) たちの。日本異質論・特殊性論である。日本の経済構造と社会慣習は反民主的であり、欧米のシステムとは完全に異質であるとする彼らは、外圧を加えてでも日本を封じ込まねば、そのがむしゃらな経済拡大によって欧米の経済は決定的に破壊されないと懸念する。
クライド・プレストヴィツツ、チャーマーズ・ジョンソン、カレル・ファン・ウォルフレン、ジエームス・ファローズといったリビジョニスト四人組は、それぞれ独自の議論を展開していて、主張内容や力点の置き方は必ずしも同じではないが、日本を特殊祝する点では共通している。ジェラルド・カーチスが示唆したように、彼らは、日本側のこれまでの日本研究が、日本社会の文化的独自性(ユニークネス)を強調しすぎたことを逆手にとって、批判的視角からの日本特殊性論を展開したのである。その場合、自分たちの欧米社会がつねに普遍的である、という大前提に立っている点を見逃してはならない。この自明とされる仮定は、欧米的バラダイムの絶対視を示すものであろう。
しかしそれは世界史的に見て十分な根拠をもつものではない。
自律的な個人の活動を基礎にして達成された欧米型の近代化とは対照的に、組織に内在するシナージー(協同化過程)の活用によって効率的に達成された日本の近代化の過程もまた、人類社会の普遍的動態だと考えられる。したがってこのタイプの近代化を判断基準にすれば、世界中で最も早く近代化・産業化を達成したとはいえ、欧米社会もまた、ある意味では一つの特殊形態であるにとどまる。文化の特性についても同様である。かくて、一方が普遍で他方が特殊であるのではなく、それぞれがともに特殊であるとする「文化相対主義」の立場からの批判が不可欠である。にもかかわらず、他社会との比較も不可能なほどに特殊な社会構造を日本は自由貿易の対象国とはなりえない、とする彼らの見解は、「文化相対主義」をまっこうから否定するものである。 |
21世紀はグローバル化が一層進む時代です。
真の意味でグローバルな視点をもつためには、異なる社会や文化を優劣の視点から論じるのではなく、文化相対主義こそが、その重要な鍵であるといえるでしょう。
※ |
参考文献
梅原猛編著『日本とは何か 国際化のただ中で』(NHK出版 1990年)
濱口恵俊編著『日本文化は異質か』(NHK出版 1996年) |
|