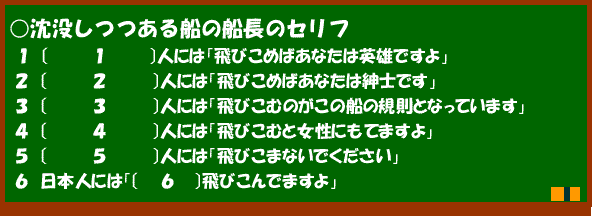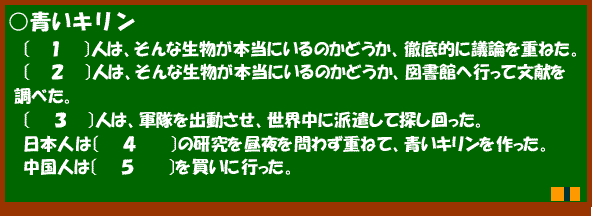|
日本人論を代表する書物のひとつに、ご存じ、アメリカ人ルース・ベネディクトの『菊と刀』があります。日本人の古典と言うべき名著です。
これからは、次の長い引用を使って、その革新の部分を学習しましょう。
| ※ |
一応、ルース・ベネディクトとその著書『菊と刀』の紹介をします。
著者はルース・ベネディクトは、1887年生、1948年没。当時のアメリカの代表的文化人類学者。 この本が企画されたのは、1944年(第二次世界大戦の末期)。当時、太平洋戦争は最終局面を迎えており、アメリカ政府としては、やがて来る日本の敗北・占領という事態に備え、自分たちとは異なる思考様式・行動様式を持つ日本人について、敗北の最後の抵抗の程度や占領政策の具体的方法を考えるために、日本人や日本の文化に関する体系的な研究が必要であった。ベネディクトは、その研究チームの一員として日本人や日本社会を研究し、その成果をこの本にしました。 出版は大戦終了の翌年の1946年。日本でも1947年に初めて出版され、それ以来長く読み続けられてミリオンセラーとなっている。
|
※ |
長谷川松治訳『菊と刀ー日本文化の型』(社会思想社1972年版)から引用しました。行間設定は引用者が行いました。 |
|
「 このように、慎重と自重とを全く同一視するということの中には、他人の行動の中に看取されるあらゆる暗示に油断なく心を配ること、および他人が自分の行動を批判するということを強く意識することが含まれている。彼らは、「世間がうるさいから自重せねばならない」とか、「もし世間といものがなければ、自重しなくともよいのだが」などと言う。こういう表現は自重が外面的強制力にもとづくことを述べた、極端な言い方である。正しい行動の内面的強制力を全然考慮の中に置いていない表現である。多くの国ぐにの通俗的な言いならわしと同じように、これらの言い方も事実を誇大に表現しているのであって、現に日本人は時によっては、自分の罪業の深さに対して、ピューリタンにくらべても決してひけをとらないくらいに強烈な反応を示すことがある。とはいうもののやはり上の極端な表現は、日本人がおよそどういうところに重点を置いているかということを正しく指摘している。すなわち、日本人は罪の重大さよりも恥の重大さに重きを置いているのである。
さまざまな文化の人類学的研究において重要なことは、恥を基調とする文化と、罪を基調とする文化とを区別することである。道徳の絶対的標準を説き、良心の啓発を頼みにする社会は、罪の文化 'guilt culture' と定義することができる。しかしながらそのような社会の人間も、例えばアメリカの場合のように、罪悪感のほかに、それ自体は決して罪でない何かへまなことをしでかした時に、恥辱感にさいなまれることがありうる。例えば、場合にふさわしい服装をしなかっことや、何か言い損ないをしたことで、非常に煩悶することがある。恥が主要な強制力となっている文化においても、人びとは、われわれならば当然だれでも罪を犯したと感じるだろうと思うような行為を行った場合には煩悶する。この煩悶は時には非常に強烈なことがある。しかもそれは、罪のように、懺悔や贖罪によって軽減することができない。罪を犯した人間は、その罪を包まず告白することによって、重荷をおろすことができる。この告白という手段は、われわれの世俗的療法において、また、 その他の点に関してほとんど共通点をもたない。多くの宗教団体によって利用されている。われわれはそれが気持を軽くしてくれることを知っている。
恥が主要な強制力となっているところにおいては、たとえ相手が懺悔聴聞僧であっても、あやまちを告白しても一向気が楽にはならない。それどころか逆に、悪い行いが「世人の前に露顕」しない限り、思いわずらう必要はないのであって、告白はかえって自ら苦労を求めることになると考えられている。したがって、恥の文化 'shame culture' には、人間に対してはもとより、神に対してさえも告白するという習慣はない。幸運を祈願する儀式はあるが、贖罪の儀式はない。
真の罪の文化が内面的な罪の自覚にもとづいて善行を行うのに対して、真の恥の文化は外面的強制力にもとずいて善行を行う。恥は他人の批評に対する反応である。人は人前で嘲笑され、拒否されるか、あるいは嘲笑されたと思いこむことによって恥を感じる。いずれの場合においても、恥は強力な強制力となる。ただしかし、恥を感じるためには、実際その場に他人がいあわせるか、あるいは少なくとも、いあわせると思いこむことが必要である。ところが名誉ということが、自ら心中に描いた理想的な自我にふさわしいように行動することを意味する国においては、人は自分の非行を誰一人知るものがいなくても罪の意識に悩む。そして彼の罪悪感は罪を告白することによって軽減される。
アメリカに移住した初期のピューリタンたちは、一切の道徳を罪悪感の基礎の上に置こうと努力した。そして現代のアメリカ人の良心がいかに罪の意識に悩んでいるかということは、すべての精神病医の承知しているところである。しかしながらアメリカでは、恥が次第に重みを加えてきつつあり、罪は前ほどにははなはだしく感じられないようになってきている。アメリカではこのことは道徳の弛緩と解されている。この解釈には多分の真理が含まれているが、しかしそれはわれわれが、恥には道徳の基礎というような重圧を果たす資格がないと考えているからである。われわれは恥辱にともなう烈しい個人的痛恨の情を、われわれの道徳の基本体系の原動力とはしていない。
日本人は恥辱感を原動力にしている。明らかに定められた善行の道標に従いえないこと、いろいろの義務の間の均衡をたもち、または起こりうべき偶然を予見することができないこと、それが恥辱(”ハジ”)である。恥は徳の根本である、と彼らは言う。恥を感じやすい人間こそ、善行のあらゆる掟を実行する人である。「恥を知る人」という言葉は、ある時は
'virtuous man' [有徳の人]、ある時は' man of honour' [名誉を重んじる人]と訳される。恥は日本の倫理において、「良心の潔白」、「神に義とせられること」、罪を避けることが、西欧の倫理において占めているのと同じ権威ある地位を占めている。」 |
ベネディクトの考えは、次の様にまとめることができます。(上の文章を読んで表を完成させてください。)
恥の文化という発想は、なかなか鋭い分析です。
他者の目が必要という点では、、次のようなお話が伝わっています。
|
昔あるところに、貧しい父親と息子がいました。父親は、常々こう言っていました。
「お天道様が見ているところでは、悪さはしてはいけない。」
ところが、貧しさ故に食べるものがなくなった親子は、空腹に耐えかねて食べ物を盗んでしまいます。夜陰にまぎれて人の畑に侵入し、野菜を持ち去ろうとした時、子どもが叫びます。
「お父ちゃん、盗んだらあかん、お月様が見てござる。」
2人は、煌々と輝いている満月を見て、首うなだれて野菜をおいて帰ります。
この話は、「どこで誰が見ているかもしれず、悪いことをやってはいけない。」という道徳話です。 |
多くの日本人は、この話を聞いて、なるほどと思います。
数年前でしたが、岐阜県議会のある議員さんが、県議会の一般質問でこの話を題材にして教育論を語り、「道徳教育をしっかりやらなければいかん」と結んでおられました。
議場では、多くの方が納得されておられました。
しかし、よく考えると、おかしなものです。
このような道徳律では、「太陽も月も、誰も見ていないところでは、何をしてもよい。」ということになってしまいかねません。いかかでしょうか。それでも、これが日本人の常識的な発想なのです。
本来、誰かが見ているとかに関係なく、「ならぬものはならぬ」はずです。
|